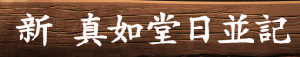棟札発見!

手水舎の工事をしている大工さんに、「棟札がありました!」と報告を受けました。
足場を登って、桁などを跨ぎ、不安定な足元を棟木の真下に行って見ると、立派な字で書いた棟札がありました
逆光のところを写真を撮って、後から見ると、このように書かれていました。
享保十九年甲寅歳二月 大工 川合 安藝
【梵字】奉喜捨 井戸屋形一宇 施主 信濃屋与三次郎
鈴聲山二十八世 上乗院前大僧正 尊通 役者 祥源院 道尊
東陽院 道尊

享保19年は、西暦で1734年。徳川吉宗の頃です。真如堂は1703年に本堂を上棟し、1705年に28世尊通の勧進によって現在の伽藍を建立して、入仏供養をしています。
手水舎は、総門や元三大師堂に続いて寄進によって建てられ、それは鐘楼などよりも早かったことがわかりました。
尊通師は、藤原北家の流れを汲む正親町家の出身で、重文の「寒山拾得図」は師の持ち物でした。「役者」は執事のことで、名前から、二人とも尊通師の弟子であることが推測されます。
小屋組を見ると、その後に修理された跡がありますが、棟札があることは今日まで明らかにはなっていませんでした。
お寺の歴史がわかる、うれしい大発見でした!